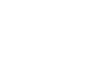人の手を感じられる「本質」の追求。
View from the Carpet #1 ONOHOUÉ
安らぎのある情景、温もりが感じられる空間は、長い年月をかけて育まれるものです。
その足元にひっそりと佇む、一枚のカーペット。ふと眺めてみれば、そこには「その人らしさ」や「生き方」が織り継がれていました。

堀田カーペット株式会社の三代目堀田将矢が、カーペットのある風景をめぐる連載企画。第一回は、大阪・谷町四丁目のフレンチレストラン「ONOHOUÉ(オノウエ)」のオーナーシェフ、阪本充治さんを訪ねました。
人の手を感じられる料理がしたかった。
駅前の賑わいを抜け、閑静な住宅街に建つ一棟のマンション。エントランスの手前には地下へと続く階段があり、その先を進むと、吹き抜けの開放的な中庭が現れます。枯山水のような趣の緑を見渡す大きな開口のテラスが特徴的な店内は、温かみのある土壁を基調に、青色のカーペット、クラシカルな調度品がぴたりと揃います。

 阪本(以下 S):1970年代のフランス料理がしたかったんです。いわゆるエスプリの効いたクラシックなキュイジーヌフランセーズを、その頃のレシピでやりたかった。なので、店内の雰囲気も南仏の田舎をイメージしています。
阪本(以下 S):1970年代のフランス料理がしたかったんです。いわゆるエスプリの効いたクラシックなキュイジーヌフランセーズを、その頃のレシピでやりたかった。なので、店内の雰囲気も南仏の田舎をイメージしています。
堀田(以下 H):なぜ、70年代なのですか?
S:現代のフランス料理は、最先端の調理器具ばかりで。料理人が作っているのか、機械が作っているのかわからない。人の手をどんどん感じられなくなってきていて。だからうちには、電気の調理器具は一切置いていない。ミキサーも絞り器も、食洗機も。全部手でやっているんです。
H:全て手作業! まさに、手間を惜しまずに作られた料理ですね。
(インタビュー前にコースをいただき)「秋刀魚のポタージュ」に感動しました。秋刀魚ってどうしても臭みを感じる食材だと思っていたから。

S:ゆっくり、ゆっくりスープにしているので、いい部分ばかりが集まる。本来の秋刀魚の味って、甘みもあるし、苦味、旨味も鉄分も全て入っているんですよ。
H:あんな風にして食べたことがなかったですけれど、ちゃんと秋刀魚の風味が感じられて、僕の知っている秋刀魚の雑味を全て無くして、いいところだけを味わった感じがしました。
S:あのポタージュには、肝も全部入っているんです。秋刀魚のマリネも一緒に出しましたが、きっとポタージュの方が美味しく感じられたでしょう。例えるならば、秋刀魚の刺身の方が葡萄で、ポタージュの方がワインなんですよ。
ワインの葡萄だけ食べても、テロワール(大地)の意味合いは分からない。でも、ワインという、人の手が加わって、醸造という時を経て、テーブルに現れるとき、はじめてみんなに分かるようになるんです。


H:料理にはじまり、食器、空間。どこかで妥協してしまいそうなものだけれど、それを感じさせない空間づくりと演出を感じながら、お食事をいただきました。
S:食器は、どれもオリジナルでデザインされたものです。100年前のアンティークのお皿をベースにして、知り合いのデザイナーに頼んで焼いてもらいました。
壁も、京都の左官屋さんに全て手で仕上げてもらったもので、ガラスサッシも、古いステンドガラス。(エントランスの方を指差して)あの入り口も裏は事務所なんですけれど、導線のために必要な入り口だったんです。でも、お客さんの視界には絶対にいれたくなくて、洞窟風の形にしてみたり。

H:店舗のインテリアって、いわゆる「アンティーク調」で ”ぽく”なりがちですけれど、ここで「本質的な良さ」ということをすごく感じました。どこかがズレていると、この空間は絶対に生まれてこないですよね。
S:だから、絶対にカーペットにしたかったんですよ。やっぱり、フランスの星付きレストランはどこも絶対にカーペットなので、僕らからしたら憧れの存在。
H:それは、嬉しい! 実際に使ってみて、いかがですか?
S:まず、落ち着くでしょう。これだけの幅をカーペットにすると、お客さんも「あっ」と気が付いてくれる。ここで横になりたいわ、っという人もむちゃくちゃ多い(笑)。ここで寝れるくらいって、ものすごいくつろぎの空間だということですよね。
あとは、音がならない。静か。これって、レストランでは大事なことなんです。
なにより、スタッフの足も楽ですしね。これ、タイルとかだったら疲れるんですよ。

H:逆に、使いづらいと感じることはありますか?
S:今のところ、思いつかないですね。でも、ワインとかこぼしたらドキッとはするかも。今後使っていったらどうなっていくんだろう。
H:これまでにホテルのバンケットルームなども手がけましたが、どうにかなるってことはないと思います。20年とか経てば、もちろんへたってきたりはすると思うけれど、鮮やかな感じから、また一味違ったエイジング感がでてくると思います。
「人がいるほうが綺麗に見える」

H:ネイビーを選んだのはなぜですか?
S:最初はブラウン系の色も候補だったんです。でも、土壁にしようって思っていたから、同系じゃなくて、スクッとした、高級感がある色を、と決めました。(店内に搬入するインテリアの中で)絨毯が最後だったから、入った瞬間に一気に「レストラン」になりましたね。
H:僕らがカーペットをやらせてもらうときって、家具が入っていません。オーナーさんはある程度のイメージができていると思うけれど、僕らはわからないまま。なので、完成後にお店に呼んでいただいて、めちゃくちゃ素敵だなって!
S:そういえば、前に社長さん(二代目 堀田繁光)が「人がいるほうが綺麗に見える」と言っていて。本当にそうだと思いました。建物に来て、設えられて。やっぱりここを歩く人、使う人がいて、良さというものが出てくる。

H:そうか。それ、うちの親父が言っていましたか・・・良いこと言っているね(笑)。
実は、僕が「CARPET LIFE」を撮影するときに意識しているのも、必ず人が入っている写真を撮ることなんです。やっぱり、人がいないものって、物足りない。人のためにつくっていると思っているので、そこで何かを感じてもらうことが、カーペットが生命を帯びる瞬間なんです。
S:それは、フランス料理も一緒。僕は「生命の移り変わり」だと思っているんです。例えば、さっきの秋刀魚が水揚げされたとき、一旦生命は終わる。でも、僕ら人間が食べることによって第二の生命ができる。だから、その料理は絶対に最高でなくてはならないんです。ただ、塩焼きにする、お造りにするのではなくて、より秋刀魚の味がしなくてはと。
H:うんうん。こうして話を聞くと、料理の価値をますます感じられるし、もう一度食べたいなと思います。できあがったものには、そこに行き着くまでのストーリーがたくさんあって。それを伝えていくことって、最初は難しいんだけれど、丁寧に伝えていきたいなと。

S:本当は、無言でも受け手が感じてくれたらいいのですが。言葉で伝えるのは、難しい。どうしてもチープになってしまうから。よく「シェフが見つけてきたどこそこ産の食材で、朝からああして、こうして、何時間かけて」なんて、めちゃくちゃ説明してくれるお店もあるけれど、そういうのは言わないほうがいいのに、っていつも思う(笑)。今の時代は、そういうところがズレているなと。
H:ズレている?
S:例えば、ワイン。最近ではコルクじゃなくてスクリューキャップになってきている。そうすることで「ブショネ」って言って、腐敗したコルクでワインが悪くなる問題がなくなるんです。
でも、あれって完全に本質からズレている。スクリューキャップでは、ワインは熟成しないんです。時間が経つにつれて、どんどん素晴らしいものになっていく。そういったワインが持っている本質、資産価値を人間が崩すというのは、明らかにおかしい。

H:なるほど。そういう意味では、カーペットも、どんどん本質を見失っていて。安かろう悪かろうといったものがかなり増えているんですけれど、そういうことを提供していくと、それがお客さんの普通になってしまって、市場から本質的なものが消えていってしまう。
僕が思うカーペットの本質は「長く、気持ちよく使ってもらうこと」。それ以外は単なる意匠でしかないから。そこを見失うと、メーカーとして絶対にダメ。もちろん、意匠性も大事だけれど、カーペットは空気を作るものだと思っているので、例えば、阪本さんが集めたアンティークが引き立つものでなくてはならない。カーペットが主役になってはいけなくて。だから、この空間に綺麗に馴染んでくれているのがとても嬉しかったです。

感じてくれる人がいて、はじめて成り立つこと。
S:でも、それって相手が何とも思ってくれなければ伝わらないでしょう。うちの料理も「なんで機械やめたん?」って聞かれるけれど、いままでワープロで書いていた手紙を、手書きに変えただけのことなんですよ。それを「あ、手で書いてくれた葉書なんだな、心がこもってるな。」って思ってもらえないと。
理由は、僕自身が手作業でつくった料理の方が美味しいって感じるからだけれど、それは感じてくれる人がいてはじめて成り立つことで。自分だけのものになってしまうのは、良くない。大事なのは「相手に喜んで欲しい」って、それだけのことなんですけれどね。
H:その気持ち、大事ですね。そういえば、なぜ阪本さんは料理人になろうと?
S:20歳で行った、はじめてのフランスで。当時三つ星のレストランだった「TOUR D’ARGENT(トゥールダルジャン)」に行って感動して。だから料理人になりたくてフランス料理をやっているのではなくて、フランス料理の料理人になりたくて、この道に入ったんです。

H:なぜ、フランス料理だったのでしょう。
S:たまたまではなくて。テレビでアラン・シャペルの特集がやっていて、トゥールダルジャンが紹介されていて「ここで食べてみたいな」と思ったのがきっかけです。
それから、料理学校に行くようなお金もないし、3年後に行こうって決めて。
フランスに行く前に、何か持っている技術がないと通用しないだろうと、まずは魚の勉強をしました。日本は、やっぱり魚がすごいし、フランス人はあまり知らないだろうと思って、魚について何でもよく知っていたり、早くさばけたりすれば、重宝されるだろうと。だから、市場に行ったり、魚屋さんに勤めたり、食材の勉強ばかり。7年間フランスで勉強して、30歳で戻ってきたら、大阪で自分の店をしようと思っていたから。

H:その頃の目標を見事に叶えたのですね! ちなみに、ONOHOUÉ(オノウエ)という店名はどうして?
S:うちの親父の苗字だったんです。子供の頃、阪本に養子に来て、母親と結婚した。オノウエは5人兄弟だったけれど、みんな早くに亡くなってしまって、子供が一人もできなかったと聞いています。僕は、叔父にものすごく可愛がってもらっていて。料理人を志した頃に亡くなってしまったから、叔母と親父に「自分が将来、独立して店をやるときは、オノウエって名前にする」って約束したんです。叔母と親父も忘れていると思うけれど。
H:この先、お店をどうしていきたいですか?

S:明日のことも、よくわからないです(笑)。でも、ずっと昔から言っているのは、フランスで店がしたい。フランスで店をやることになってもオノウエってつけたいから「ONOHOUÉ」。日本のローマ字だと発音ができないので、フランス人の友達と考えて、はっきり読んでもらおうと。
H:それも、ブランディングですね。
S:でも、この店は誰かに使ってほしいですね。細かいところまで考えぬいて作った空間は、やはり思い入れがありますから。

オノウエ (ONOHOUÉ)
大阪府大阪市中央区糸屋町1-1-6 B1F
Photo : Keisuke Ono
Text : Hiromi Nagano